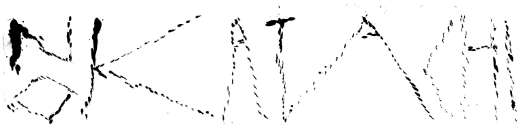2025/08/05 23:24
2024年版
郷土と人の混ざりあいの態度
この年は初めて参与観察をした。そのため農作業は使用者として父母を手伝いながらその動向を観察という態度をとった。 とは言え、参与観察のことなんてよくわからなかった。5年前から吉勝制作所にお世話になっている中で、本を読んだり制作したりすることに、 関わらせてもらっている中で、私が実家に住みながら農作業をすることになった。それまで読んだ本の議事録みたいなものを書き溜めていたため、 せっかくだから参与観察をしながら文章が書けるんではないかとなり始まった。ような気がする。理由はあまり覚えていないが、やってみようということにはなった。 しかし難しかった。農作業の傍らで、頭はずっと文章を何書くかを考えていた。部屋の壁に書いた文章を貼って客観視してみたり、図を書いて考えてみたり散々した。 それを吉田さんに見てもらって、文章が飛んでいて分かりづらいから具体的に書いてと言われそれを修正したり、レイアウトもしてもう完成だと思って印刷工場に行ったら、 本当に直前まで検討した。むしろ軽く終わらなかった。でもそこにはこういう本にしないといけないからこうして。という枠がなくて、一緒にどう作るか。を検討しまくる 時間だったから、すごく楽しかった。だから、こうなったんだという本になった。本を開けば、内容よりもその態度が目に付く。私は参与観察をしているという態度が痛々しい。 特に文章内に「おこないの跡」という言葉がちょいちょい出てくる。音読会仲間の多田さんがこちらに遊びに来た時に、本の感想として気になったところを教えてくれた。 なんでそこが気になったのかまでは聞けなかった。初めて書いた文章の内容に自分が入り込んでいてくすぐったい。文章の出来事には参与観察している私で入り込んでいなさそうなのに ここら辺を、2025年板では改善したい。出来事に参与観察して、文章は書いた跡ぐらいに留めたい。
人手
農家の維持方法として、人手確保に重点を置いている。なぜなら、郷土内に空いている人手はないからだ。いる人は 皆何がしかの職についている。年寄りだってその人たちのネットワーク内で需要があり忙しい。同年代はだいたい役場に勤めているか 後継としての生産者だったりする。この地に都市よりも条件の悪い給料をもらいにくる人はいない。給料ではない何かの理由がある人 しかいない地で、関係がない人へ働き手として募集をかけること自体が間違えている。そのため、既存の募集方法で興味を持ってもら えるのは、この地に関係がまだ結ばれていない学生を相手にするしかないということで、農林大学校に電話をして学生に募集をかけて いいかを聞いた。そしたら1人来てくれることになり、今、一緒に朝の時間畑で農作業をしている。他には、以前、畑でご飯会をしたときに 来てくれた阿部さんが今年も来てくれている。上半期は加工場で漬物の製造をお願いしていたが、60アールの状況が変わったため、畑での 農作業をお願いした。この2人に手伝ってもらいながら、アスパラガスの生育に必要な手間を畑にかけている。
参与観察という技術
オンライン音読会が一年以上続いている。2025年の今年は贈与論を読み終わって負債論に入った。 冬の手伝いで吉勝制作場に伺って仕事前に本読みをしていた頃が懐かしい。 私は、贈与論を読み進めているとどう解釈すれば良いかがわからない文面が登場する。そうすると図を書いて 脳内を整理する。それを音読会に投げてやり取りをするのだが、その中で関係ができてそれぞれ役割ができて、 それが制度化するみたいな内容を掴んだ。せっかく掴んだ内容なので、せっかくだからどんなもんか試したくなる。 そんなわけで、参与観察の手法に使ってみる。なるべく関係を見てみることにする。そこの出来事にある制度や 役割ではなく。どんな関係が築かれようとしているか。この関係を見ていく参与観察の技術があると、目の前の ことに向き合って対応していくかを考えるようになった。というかそれを記憶しておいて、記録として残そうと思っている。 既存の農家の農法だと人材確保の手段が欠落していた。結果として私がそうだったように、参与観察という関係の作法が 人が郷土に混ざっていくきっかけになるんじゃないかと思う。
争い
昨年、この60アールのアスパラガスの苗植えをしていて、元々は父親チームで苗植えをする予定だった。 しかし、体力の問題や他の手伝ってくれる人が家の用事で来れなくなったとかで、こちらも急遽回ってきた。 そのために私は友人に連絡した。苗植えを手伝ってくれる当日、父はやり方に口を出してきた。全体のうちでここまで
終わらせるという目標設定だ。 もちろん父は畑にいない。友人の状態や畑の天候がわからない状態で、ただ単に通常こういうやり方をするという理由だけで、 口を出して押し付けてきた。要は、その制度に当てはまれということだ。 当日は夏の炎天下の中、作業が行われた。苗植えのタイミングは父が決めている。十分な説明はない。多分農協からの苗の搬入 がそのタイミングなんだろうなどや、農作業が忙しくて連絡する余裕がないのだろうと適当に整合性を取る。農協からの連絡は 全て父を経由して私に届けられる。面倒な事はしたくないという理由から頭のどこかで管理者は適切に動いているというレッテル を貼ってしまっていた。この当時から、所有者であり管理者であった父と、使用者であった私の関係はギクシャクしていた。 2年間、農作業を手伝ってきた結果から、農作物は農協に卸して他は道の駅(産直)に卸すというのが、この地の常套手段だという事は理解していた。 農家として継続していくために、一定の収入が必要になる。その収入を得るためには一定規模まで農地拡大とそのための人手の確保が必須だった。 農地は現段階では私は手伝ってくれている人との関係から、新しく畑での役割を作っている。
農協との関わり
袂を分つのは突然だった。この60アールの畑を私に任せると言っておきながら消毒は機械の取り扱い上 父親がすることになっていた。そのため、60アールの畑がどのような状態にあるかを共に共有していた。 そうすると、なんでここまで進んでいないんだということになる。任せるという言葉のズレからいざこざに発展する。 父の任せるというのは、父の納得するやり方でやることで制度化された決まりの上で遂行していくことだったが、 私の任されたは、私のやり方でやってみるということだった。いわゆる、よくある田舎の親子の争いである。 そういったわけで、話し合いで解決ということにはならない。埋められない溝みたいなものがそこには確かにある。 なので正面衝突からの大げんかになるわけだが、売り言葉に買い言葉が繰り広げられ、意地がぶつかる。口を出させないためにも 完全に60アールから父親を追い出すしかなかった。そのためには農協の情報と出荷の権限をこちらも握るしかなく、次の日には 農協に出向き、組合員として登録を行い、畑の管理者として関わることになった。農協から年間の防除履歴という資料があり、 そこには肥料の種類や薬剤の種類と何に効くかが書かれている。月に一度、農家の圃場を各農家がグループに分かれて回る タイミングで、農協職員にどう見るのかを聞き、すぐに消毒液を農協に買いに行く。いつも卸している選果場の隣に肥料と 消毒液などを売っている建物がある。12畳程度でシーズン中は無休で開いているところなのだが、思ったよりも狭いし、何より古い。 農協職員のいる事務所をその隣にあって役所っぽい感じだし、農協の銀行も同じ土地内に併設されている。そこで口座を作って、 選果場に卸したアスパラガスの売上は、その口座に入る仕組みになっている。 登録の際、相手をしてもらった支店長がいるのだが、元々農家をしていたといっていたが、シュッとしていて田舎のおっちゃんという よりかは、スーツの似合う支店長という感じだったのが驚いた。その人とは選果場に卸していた時にも会った。どういう理由かは わからないが選果場で働いていて、その場に居て声を掛けられた。。アスパラガスは出ているかという決まり文句の挨拶と、 アスパラガスの芽は動いているかという会話だった。根っこを大きくすると同義だが、芽が動いているかという会話を今までしたこと がなかったので、一瞬呆気に取られていた。苗植えをして翌年の2年目を知っていることと、立茎の期間中だったので、こちらを心配しての 会話だったと思うが、そういう状況確認があるのかと勉強になった。それから60アールの畑のアスパラガスは、根が大きくなっているか 考えるよりも、芽が動いているかを見るようになった。 この根を大きくするとアスパラガスの収量が増える。そのため、どうすれば病気なく大きくすることができるかの手間のかけ方が問題となる。
参与観察という技術
オンライン音読会が一年以上続いている。2025年の今年は贈与論を読み終わって負債論に入った。 冬の手伝いで吉勝制作場に伺って仕事前に本読みをしていた頃が懐かしい。 私は、贈与論を読み進めているとどう解釈すれば良いかがわからない文面が登場する。そうすると図を書いて 脳内を整理する。それを音読会に投げてやり取りをするのだが、その中で関係ができてそれぞれ役割ができて、 それが制度化するみたいな内容を掴んだ。せっかく掴んだ内容なので、せっかくだからどんなもんか試したくなる。 そんなわけで、参与観察の手法に使ってみる。なるべく関係を見てみることにする。そこの出来事にある制度や 役割ではなく。どんな関係が築かれようとしているか。この関係を見ていく参与観察の技術があると、目の前の ことに向き合って対応していくかを考えるようになった。というかそれを記憶しておいて、記録として残そうと思っている。 既存の農家の農法だと人材確保の手段が欠落していた。結果として私がそうだったように、参与観察という関係の作法が 人が郷土に混ざっていくきっかけになるんじゃないかと思う。
武田さん
前回、くるみ味という美味しいの方言がある話を書いたので、今回は郷土の料理が作れればと思い、以前、畑でご飯会をした時に参加してくれた 料理人の武田さんに、「郷土と人の混ざりあい」から自然に対しての人の関わり方から何か料理を作って欲しいとお願いをした。個人的には当初、 岡山県にいるからそこの地で、考えうる関わりから料理を考えてもらえるかなと思っていたが、zoomで会話をしていると、こちらのアスパラガスを 送って欲しいと依頼があたのでこちらのアスパラガスとその時期に採れる赤ミズという山菜、山椒を送った。 お忙しい中で受けてくれたのはすごく嬉しいが、なんで受けたんだろう? オンラインで聞き書きをさせてもらいたい。
阿部さん
阿部さんには、昨年母の記録をお願いしていた。建築畑出身で以前、ご飯会に参加してくれてそこから週に一回、 3年前ぐらいから手伝いに来てくれている。母の暮らしを記録したくて息子の私が直接聞き書きするよりも、阿部さんを介して 聞き書きした方が、他人の方が当たり前が当たり前じゃないことが多そうで都合が良いかなと思いお願いした。当初の決め事で 春夏秋冬で分けて記録することにしたが、進めていくと母は一年間を、春植え-夏植え-アスパラガス農作業-漬物加工と作業で 区切っていることがわかった。 ここら辺が郷土に人が混ざりあった結果なのかもしれないと思っている。畑と近くの山、関わり合う人が 一定の規模の範囲にいて、それが葬式の関わりを動力に動いている。そこに、おサイトウや道の駅の出品者の役員会など集まりごとで、 共同体感が機能している。 阿部さんは他に二つの農家でも手伝いをしている。そういった農家間を比較して見ながら、暮らしを眺めてみてどのように思ったのか聞き書きしてみたいが、なんで受けたんだろう?
・・・
8/5の当初のたたき台
「料理は誰のもの?」
美味しいが交わることはない。食卓で交差される美味しいねという言葉は誤訳されて相手に届く。
だからなのか、美味しいはその場を明るくする魔法の言葉だ。(環世界を維持する作法)
・・・
婆さんのいた頃は田んぼとしてあったところを、昨年アスパラガスを生育できる環境になるよう土を盛った。
2025年は農家をしている。アスパラガスを生産していて出来た物は農協に卸している。そのほかに道の駅にも卸している。なので一年のほとんどをアスパラガスで生計を立てている。だから、アスパラガス圃場に立ってアスパラガスのことばかり考えている。収穫のこと、水のこと、土のこと、消毒のこと、肥料のこと、アスパラガスを元気に育てることに関係する要素は全部考える。
特に所有管理している60アールの畑は、2/3をアスパラガスに1/3を自家菜園に割り当てている。毎日のように居るから自ずと厨房のように綺麗にしたいし使い易いように整理したいと思ってくるが、それ以上に厨房の料理を作るだけの空間としてだけではなく、スタッフをお客として招く食卓でもあるし、アスパラガスの端材を捨てて堆肥化したものを他の野菜にまわして、その野菜の枯れた茎を堆肥化してアスパラガスに使うという仕入れ先の棚のようでもある。自家製と名のつく調味料を発酵させておく瓶の中のように、土壌を育てたいし、食材の使い残しがないようにアスパラガスの全部を畑に還元させたい。
美味しいが飛び交う食卓と同じように、気持ちがいい農作業を目指している。
そんな事を意識しながら農作業を計画していても、雨が降ったり風が強かったり、干ばつが続いたり状況は刻々と変化していく。消毒や除草剤ばかり撒いていると土が痩せる。かといって菌液を撒いて土壌を活性化させると雑草が増える。だから土壌が元気になって雑草が生えてくる前に防草シートを敷いてみる。
私はその時々に畑との関係を見極めながら役割を変え応答していく。したい役割だけをしていると畑が廃墟化していく。特に今年は干ばつが続いたため、収穫作業ばかりに精を出して灌水を怠っていると、地面にヒビが入って畑が痛がっているように思えてくる。そうすると、今度はどう灌水をするかばかりに意識がいき、収穫作業がおろそかになってしまう。灌水設備を導入していない畑での人手も足りていない状況だと、1人何役もこなさなくてはいけない。それはそれで畑の管理を隅々まで見れるから、状況を分かると言う上で必要な事でもある。その代償として身体が悲鳴をあげることさえ目をつむることが出来れば、勝手に動く身体を止めないでずっとやっていられるけど、そんなのサスティナブルのかけらも無い。
地域の人たちにさらされる畑の「所有者」として、上手な「管理者」の立ち位置も農道や用水路の共有財、農協を活用する上で、その役割だってそれなりに必要だったりする。
個人的によくわからないのは、この「所有者」と「管理者」の区分だ。
なんでこれを考えるに至ったかは、農協から配られる資料に各農家のアスパラガス圃場と書いてあって、畑ではなく圃場を使っているところが気になった。
圃場とは、農業試験・研究・行政・計画などの文脈で使われる「農作物を育てるために整備された土地」の総称。となっている。
畑だと思っていたところが、改めて「管理者」になって圃場だと思い知った。確かにアスパラガスの生産性を向上させるために農協からやり方を教えてもらっている。それは新庄市にある試験場での試行錯誤したアスパラガスの生育の研究成果を農協会員だから教えてもらい、その分たくさん育てて出荷して20%程度の手数料を農協に収める構造を使わせてもらっているから圃場なんだと納得できる。
ここらへんは納得できるけど、畑の「所有者」としての立ち位置はどんな意味があるのかよく分かっていない。権限上効力がある証明ぐらいで「管理者」がいないとその価値だって出来ないんじゃないかとすら思っている。もし1人で農家をしていれば、農家という言葉の中に「所有者」「管理者」「使用者」が潜んでいる。それに「管理者」は使用者の代表としての立場だと私は考えている。「所有者」としては1人で管理できる規模でもないから尚更スタッフという他の「使用者」は居て欲しい。そもそも土だって虫だってこの畑の「使用者」だし、畑を使用するスタッフだって何かの「管理者」だし、私も畑の虫の環世界の「使用者」でもある。消毒やら除草剤やらでその世界を壊しているから破壊者かもしれないし、どちらかといえば、どこにあるか分からないベルトコンベアから流れてくる肥料製造工場の「使用者」でしかない。
「使用者」が制度を決めないと変な話になってくるみたいな事なんだけど、例えば、スタッフの阿部さんと話していて時給の話になった。そもそも時給を仕事の「所有者」が決める風潮がよく分からない。この仕事だって一時だけ私が預かっているに過ぎない。つまり「所有者」は時系列的に考えればその前後の「賃貸者」と捉え直すことが可能である。
私の仕事場でも時給を考えるとき、年間売り上げから人件費を考慮して、さらに労力を評価してなんて決めてはいない。大体近所のコンビニがどれぐらいだから、うちもこれぐらいにしないといけないかな程度にしか考えられていない。
昨年ぐらいからニュースで騒がれている2020年代中に全国平均1500円へみたいなこともよく分からない。1500円もらえてもきつい仕事なら嫌だし、1000円でも楽しくおしゃべりしながら仕事をして結果的にもらえるんならそっちの方が私は良い。つまり、時給が決まってあって提示された仕事先を選べる自由よりも、居たい場所の時給を1500円でも1000円でもこっちが選べる、決められることが重要だと思っている。しかし、自分のところで出来てはいない。
そんなわけで、100年前に小作人の地位向上のために協同組合を創設した農業の経緯にならって(実際にそうなっているかは別として)、「所有者」「管理者」「使用者」の立場を区分して、「使用者」の立場で畑から広がる郷土までの制度を、既存の農協ネットワークを使い倒しながら、改めて郷土との関係を築いていきたい。
これが昨年から続く「郷土と人の混ざりあい」を考えながら農作業をやっていて行き着いた慣れだから、どんなおこないの跡があったか思い返さないといけない。おこないの跡は1人じゃ思い返せないから周りに聞いて書いていこうと思う。どんな関係から、そこにどんな作法があって、どんな役割で、どんな制度になっているのか。