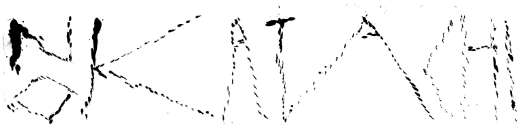2024/02/24 18:11

誰かが亡くなると、そこからの3日間は、日々の手の動きが変わる。
ただ喪に服すのではなく、食べ、迎え、送り出すための“段取り”が始まる。
1日目|迎えの支度
朝、訃報が届くと、手伝いに家へ向かう。
まずするのは、家のなかを整えること。襖をどかし、大掃除をする。場を清め、空気を整える。
いちばん最初に作るのは、小さな団子。白玉粉を10個分ほど。
「亡くなった人が、帰ってくるから」と、昔から決まっている。
その合間に、次の日の仕込みも始まる。
瓶詰めに使うゼンマイやワラビ、天ぷらにするトビタケや筍、なめこ、もだち。
下拵えをしながら、静かに手が動く。
夕飯は、家にあるもので簡単に。
ただ、手伝いの人たちは、2段〜3段の重箱におかずを詰めて持ってくる。
マカロニとじゃがいものサラダ——これはこの地域ならではで、水分が出ないから重宝される。
かぼちゃのサラダ、ゼンマイやワラビの漬け物、きゅうりのしなび漬け、ゼリー、寒天。
食べることが、見送ることと重なりはじめる。
2日目|整え、送る準備
朝、2人で買い出しに出かける。油揚げ、こんにゃく、厚揚げ(葬式だから三角に切る)、もやし、ほうれん草など。
昼には「饅頭揚げ」と「えご」をつくる。
近所の人が線香を上げに来るので、お茶を用意する。
その間にも料理は進む。
| 煮付け・天ぷら|えご|豆類 |
| ご飯 |汁物 |
御膳の上には、5皿並ぶ。果物は横に添える。供えるというより、「いっしょにいる」ための所作。
この日、葬儀屋と話をして、葬儀の品をみんなで決め、注文する。
話がまとまると、その場で手伝ってくれた人や親戚と一緒に食事をする。
いま決めたこと、これからのことを話しながら、食卓が囲まれる。
その場で、告別式で配る飴とお金を準備する。
習字紙で十円玉を包む。年の数だけ包むのがしきたり。
お酒も出る。線香の火は、誰かがずっと絶やさない。
遺体は「おひづり(白い着物)」に着替えさせ、草鞋を履かせる。
お化粧をし、棺に納める。生前の服や、33観音巡りの白衣や御朱印も一緒に。
その手順を、親戚たちが静かに見守っている。
「送る」というより、「手を貸す」ような時間。
3日目|送りの日
葬儀の朝は、赤飯の白豆おにぎりを家の者に食べさせる。
6:30〜7:30、朝参り。喪服の代わりに、羽織るものがある。
もともとはなかったが、祖母の代で他所から取り入れて、今では自然な流れになっている。
告別式。骨になるまでは「御霊前」。
受付では、包んだお金と飴を、来てくれた人たち全員に配る。母曰く「お礼なんだろう」。
昔は、白い餅を渡していたこともあったらしい。
受付が終わると、2人で記録と計算。
火葬が終わると「御仏前」に変わる。骨になって戻ってくる。
火葬の間、2時間ほどの待ち時間があるので、軽い食事が出る。
この3日間は「生臭ものは控える」という決まりがある。
その晩、また飲み会がある。
そして——
火葬後の食事は「精進おろし」。
刺身や肉、魚、お酒も飲んで、ふだんの食事に戻っていく。
手伝ってくれた人には、多めに作った料理を小分けして持たせる。
送るというのは、別れだけじゃない。
その家の台所ごと、みんなで担いでいくような日々。